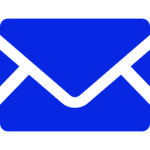1. 歯学部はなぜ進級が厳しいのか
お子さんが歯学部に合格し、「これで安心」と思っているご家庭も多いかもしれません。ですが、歯学部は「入ってからが本番」と言われるほど、進級が難しい学部でもあります。
歯学部では、基礎医学から歯科専門科目、さらには実技の実習まで、学ぶ内容が非常に幅広く、かつ深いことが特徴です。
さらに、授業や実習への出席は必須で、課題の提出や実技の評価も厳格に管理されています。
1科目でも不合格があれば進級できない場合もあり、毎年一定数の学生が留年しています。
文部科学省の調査によれば、2024年度の歯科医師国家試験を歯学部6年間一度も留年しないでストレート合格した学生の割合は、国立大学歯学部で70.9%、私立大学歯学部全体では45.0%となっています。
国立大学歯学部でも3割が留年を経験し、私立大学歯学部では半数以上の学生が留年を経験しています。現在の歯学部がどれだけ厳しいかが分かります。
「うちの子はまじめだから大丈夫」と思っていても、ほんの少しの油断や体調不良、情報不足が原因で思わぬ結果になることもあります。
だからこそ、親御さんが「歯学部での進級の難しさ」を正しく理解しておくことが、お子さんの支えになります。
2. 進級できない学生に共通する特徴
歯学部で進級できない学生にはいくつかの共通点があります。
これは本人の能力の問題ではなく、「環境」や「勉強のやり方」「生活習慣」に原因がある場合が多いのです。
(1)情報不足
歯学部の試験は、ただノートをまとめたり教科書を読んだりするだけでは乗り切れません。
学年末試験の過去問の傾向や、授業で特に重要とされるポイントを把握することが合格のカギです。
そのため、友人や先輩からの情報共有が非常に大きな意味を持ちます。
しかし、孤立してしまっていたり、人間関係がうまくいっていない学生は、こうした重要な情報が得られず、努力の方向がずれてしまうことがあります。
(2)生活リズムの乱れ
歯学部では、授業や実習は朝から長時間にわたって行われます。
夜型の生活が習慣化してしまうと、朝起きられずに出席が不安定になり、単位取得以前に進級条件を満たせなくなってしまいます。
一人暮らしの学生ほど、食生活の乱れや睡眠不足に陥りやすい傾向があります。
(3)自己流の勉強に固執する
歯学部生で、「とにかく暗記すればなんとかなる」という思い込みで、非効率な勉強法を続けてしまうケースは非常に多く見られます。「真面目に勉強しているのに留年してしまう」場合、ほとんどが「歯学部での正しい勉強の仕方」が分かっていないことが原因です。
歯学部の勉強は理解力が求められ、知識を関連づけて整理しないと試験では点が取れません。
自己流に固執し、柔軟にやり方を変えられないことが失敗につながることがあります。
(4)親に相談できない
「心配をかけたくない」「怒られたくない」「がっかりされたくない」——。
そんな気持ちから、親に自分の苦しい状況を言い出せない学生も少なくありません。
特にまじめで優しい子ほど、うまくいかない自分を認めたくなくて一人で抱え込み、問題が深刻化してしまうのです。
実は、ここで親の声かけが大きく影響します。
次の章では、どんな言葉が子どもを支え、逆にどんな言葉が追い詰めてしまうのかを含めて解説します。
3. 進級できる学生と親の特徴
進級できている学生たちに共通するのは、努力できる環境と適切な情報を得る姿勢、そして周囲からのサポートです。
それを支える親の関わり方も大きなポイントになります。
(1)規則正しい生活を意識できている
進級できる学生の多くは、まず生活リズムが安定しています。
早寝早起きを心がけ、授業や実習にしっかり出席することを最優先しています。
親としては、遠方に住むお子さんであっても「最近、朝はちゃんと起きられている?」「ごはん食べてる?」と、生活リズムを確認する声かけを意識しましょう。
体調や生活習慣の乱れは、学業のつまずきの最初のサインです。
(2)仲間づくりを大切にしている
歯学部の試験対策で必要なのは「過去問」や「情報共有」。
友人や先輩との情報交換ができている学生は、効率的に学び、試験準備もスムーズです。
「友達できた?」「試験の情報とか教え合ってる?」といった、やわらかい聞き方で友人関係について触れてみることも、親としてできるサポートの一つです。
(3)柔軟に学習法を工夫している
困ったときには友人に聞いたり、場合によっては家庭教師や個別指導を利用するなど、助けを求める力も大切です。
「困ったときは、予備校とか一緒に探してみようか?」と、選択肢を親の側から先に提示しておくと、子どもは安心して相談しやすくなります。
(4)“応援団”としての親の関わり方
歯学部で進級できる学生の親は、「責める存在」ではなく「支える存在」として関わっています。
ここで注意したいのが、つい言ってしまいがちな“NGワード”です。
■ 親が言ってはいけない言葉
・ 「なんでできないの?」
・ 「こんなにお金をかけているのに」
・ 「○○さんのところは順調らしいよ」
・ 「医学部ほどじゃないんだから」
これらの言葉は、子どもに「責められている」「認めてもらえない」と感じさせ、相談できなくなる原因になります。
■ 【おすすめの言い換え】
・ 「どこが一番難しいと感じている?」
・ 「応援しているから、何かあれば言ってね」
・ 「あなたがどう感じているかが大事だよ」
・ 「本当に大変なんだね。がんばっているんだね」
子どもは責められたいのではなく、理解されたいのです。
「あなたの努力を信じている」というメッセージを日頃から伝えることが、子どもの心の支えになります。
4. 留年は「終わり」ではない
万が一、進級できずに留年してしまった場合でも、「それは失敗ではない」と伝えることが大切です。
私立歯学部では、学年によっては2人~3人に1人が留年することもあります。特に1~2年次の基礎科目でつまずく学生は多く、むしろ「よくあること」です。
留年は、今の課題をやり直して基礎を固める大事な機会でもあります。親御さん自身が落ち込みすぎないことが、お子さんにとっては何よりの救いになります。
「時間がかかっても大丈夫。あなたのペースで進んでいいよ」と伝えることで、子どもは次に向かう力を取り戻せます。
5. 本当に困ったときは「外の力」を使っていい
どうしても一人では乗り越えられないときには、大学内の補習授業やチューター制度、歯学部進級のための予備校といったサポートを利用することも選択肢の一つです。
歯学部進級に特化した予備校なら、多くの歯学部生の進級を支えてきた経験があり、また大学ごとの状況も分かっていますので、大きな力になるでしょう。
ここで気を付けたいのは、歯科医師国家試験予備校です。歯学部の進級もやることになっていても、国家試験がメインの予備校ですから歯学部の進級についての経験も大学ごとの情報も心もとないものがあります。
デントゼミのような、オンラインで歯学部進級のための個別指導を行っている予備校なら、全国どこでも曜日や時間に関係なく指導を受けることが出来ます。
また、精神的な不調が心配な場合は、大学の学生相談室や外部のカウンセラーを利用することも重要です。
「何かあれば一緒に相談先を探そうか」と声をかけることで、子どもは「一人じゃない」と感じ、安心して助けを求められるようになります。
6. まとめ:親ができる最大のサポートとは
歯学部で進級できるかどうかは、本人の努力だけでなく、周囲の環境づくりが大きく関係しています。
親としてできる最大のサポートは、責めずに話を聞き、必要なら一緒に考えること。失敗やつまずきを否定せず、「あなたの努力を信じている」というメッセージを伝え続けることです。
子どもは、思っている以上にがんばっています。その頑張りを、理解し、応援する存在であり続けること。
それが、歯学部での6年間を乗り越える何よりの力になり、歯科医師国家試験の合格にもつながって行きます。