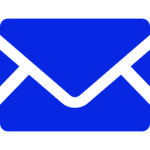1. はじめに:歯学部の厳しさと親の役割
歯学部は医療系学部の一つであり、他の学部と比べても学業負担が大きいことが知られています。解剖学や生理学といった基礎医学から、保存修復学、補綴学、口腔外科学などの臨床系科目、さらには実習や国家試験対策に至るまで、膨大な知識と技術の習得が求められます。そのため、成績不振や単位不足によって留年の危機に瀕する学生は決して珍しくありません。
では、もし自分の子どもが歯学部で留年の危機にあるとわかった場合、親としてどのように対応すべきなのでしょうか。ここでは、留年のリスクに直面している学生の親ができる具体的な支援や心構えについて、心情面・現実的な対応・将来の見通しという3つの観点から解説していきます。
2. 感情的な反応ではなく「聴く姿勢」が第一歩
子どもが「もしかしたら留年しそう」と打ち明けてきたとき、多くの親はショックを受けます。「今まで何をしていたの?」「努力が足りなかったのでは?」と責めたくなる気持ちも理解できます。しかし、最も大切なのは、子どもの話に耳を傾けることです。
歯学部で留年の危機に直面している学生は、すでに大きなストレスとプレッシャーを抱えています。親にまで責められると、自己否定の感情が強まり、うつ状態や自己肯定感の低下につながりかねません。まずは感情を抑え、いったんは「そうだったんだ」「よく話してくれたね」と共感的に受け止める姿勢を見せることが、子どもの再起の第一歩になります。
ここで親が頭ごなしに怒るばかりになると、留年ピンチもしくは留年確定の歯学部生は親に何も言わなくなります。親子の関係が崩壊してしまう恐れがあります。
とは言え、甘い顔ばかり見せるわけにも行きません。厳しい現実を親子で受け止め、子供任せにせず、これからどうすべきかを一緒に考える姿勢が大切です。
この時、大学との良好な関係も重要です。親として大学に「なぜ留年リスクが高くなったのか?」、「他の学生とどこが違うのか?」、「今後どういったことに注意していけばいいのか?」、「挽回に向けて大学はどういったことをやってくれるのか?」こういったことをぜひ大学と十分に話し合ってください。
歯学部で学ぶ大学生ですから進級・卒業に向けて、大学との良好関係作りは欠かせません。
3. 「なぜ成績が伸びないのか」を一緒に分析する
留年の原因は単純な学力不足だけではありません。そこにはさまざまな要因が複雑に絡み合っています。たとえば、以下のようなケースが考えられます:
・ 勉強方法が非効率で時間ばかりかかっている
・ 試験の形式に合った対策ができていない
・ 実習のスケジュールやレポートに追われて復習が追いつかない
・ サークルやアルバイトに時間を取られすぎている
・ 精神的な不調や人間関係のトラブル
これらの背景に何があるのか、子どもと一緒に話し合い、必要であればカウンセラーや学習支援センターに相談することも検討すべきです。親が一緒に原因を整理し、「じゃあこれからどうすれば良いか」を考える姿勢を見せることが、本人にとって大きな安心感につながります。「親は最大の支援者」だと認識させてください。
4. 経済的・スケジュール的な影響を冷静に把握する
歯学部での留年は、1年分の学費・生活費の追加負担を意味します。私立歯学部であれば、1年間の学費だけで200~500万円程度かかることが多く、決して小さな額ではありません。加えて、国家試験の受験が1年遅れることで、歯科医師としての収入開始時期も後ろ倒しになります。
この点を現実的に把握し、家計の見直しや奨学金制度、学費延納制度の利用可否などを検討する必要があります。ここでも大切なのは、子どもを責めることではなく、「どうすれば再スタートを切れるか」に焦点を当てることです。
歯学部に通う学生は誰もが、「親に迷惑を掛けたくない」という気持を持っています。
子供に必要以上のプレッシャーを掛けることの無いように気を付けてください。
歯学部生の多くはアルバイトもしていませんので、「お金を稼ぐことの大変さ」を分かっていません。私立歯学部の1年分の学費負担は、けして楽なことではないことも、さりげなく分からせるといいでしょう。
5. 「再チャレンジできる環境づくり」を優先する
子どもが再び学習意欲を持ち、留年を乗り越えていくためには、「失敗してもやり直せる」という安心感が欠かせません。そのために、親ができることは大きく分けて以下の3つです:
・ 日常的な声かけ:「この調子」「一歩ずつで大丈夫」
・ 家庭内の理解:「集中できる学習環境づくり」「生活リズムのサポート」
・ 外部支援の活用:「歯学部進級対策予備校」「家庭教師」「メンタルケアの専門家」
特に、歯学部の進級対策には専門的な知識と経験が必要です。そこで親が積極的に検討したいのが、「デントゼミ」のような歯学部進級対策に特化した予備校です。こうした予備校は、定期試験対策や実習のサポート、学年ごとの進級基準に精通しており、個別に学習状況を分析したうえで的確なアドバイスが受けられます。
オンラインでの個別指導であれば、どこにいても歯学部進級に向けて的確な指導を受けることが出来ます。
一方で、歯科医師国家試験対策に特化した予備校(通称“国試予備校”)は、進級に関する支援のノウハウが乏しいことが多く、卒業前の段階ではあまり効果的ではありません。実際、進級前に国家試験向けの教材や講義に取り組んでも、今直面している学年末試験や再試験に直結しないことがあり、時間と労力のロスになりかねません。
だからこそ、進級危機の段階では「進級特化型」の予備校を選ぶのが賢明な判断です。親が情報を集め、必要であれば面談や体験受講などもサポートしてあげると、本人も安心して学習に専念できるようになります。
6. 将来のキャリアに希望を持たせる
「留年=人生の失敗」と捉えてしまう学生は少なくありません。しかし、実際には留年を経験した歯科医師は少なくないですし、その後に成功を収めているケースも数多く存在します。大切なのは、「今つまずいても、それが将来の成長につながる」というメッセージを親が伝えることです。
また、留年を機に自分の勉強スタイルを見直し、国家試験を一発合格した学生も少なくありません。歯科医師という職業は、長い目で見れば数十年にわたるキャリアになります。一年の遅れを過度に悲観せず、「この一年が成長のための時間になる」と前向きに捉えることが、親としてできる最大の励ましです。
7. 終わりに:親としてできる最大の支援とは
子どもが歯学部で留年の危機にあるとき、親にできることは「責めること」ではなく「寄り添うこと」「支えること」「一緒に乗り越えること」です。感情的になるのではなく、冷静に現状を見つめ、共に解決策を模索する姿勢こそが、子どもにとって何よりも心強い存在となります。
人生には思いがけないつまずきがつきものですが、その一つひとつをどう受け止め、どう乗り越えていくかが、本人の成長を左右します。親として、そのプロセスを支えられる存在であることが、将来、子どもから感謝される日につながるでしょう。