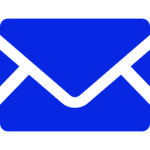1. はじめに
歯学部に進学するということは、将来の医療を支える責任ある職業に就く第一歩です。しかし、その道のりは決して平坦ではありません。特に私立歯学部では、想像以上に多くの学生が進級に苦しみ、場合によっては留年や放校にまで至るケースもあります。本記事では、歯学部生が進級の壁を乗り越えるために、予備校というリソースをどう活用するべきかを詳しく解説します。
2. 私立歯学部の進級事情
私立歯学部は国家試験の合格率向上を目指し、学内試験の難易度を年々高める傾向にあります。その結果、進級のハードルは非常に高くなっており、学年全体の2〜3割が進級できないといった話も珍しくありません。 さらに、進級試験だけでなく定期試験、再試験、再々試験、そして出席状況までが厳しく管理されています。成績不良や欠席が重なると、即・留年という厳しい処置が下されるのが現実です。 文部科学省が発表している歯学部に関するデータには、「大学別最低修業年限での国家試験合格率」というデータがあります。これは歯学部で一度も留年することなく、歯科医師国家試験も卒業と同時に一発合格した学生の割合を示すものです。 第117回歯科医師国家試験の結果で見ると一度も留年することなく国試一発合格者の割合が最も高い歯学部は91.7%の岡山大学歯学部でした。国公立、私立を合わせて29ある歯学部の中で最高でも91.7%で、1割程度の歯学部生はストレート合格とは行っていません。旧帝国大学の九州大学歯学部では54.7%でした。どれだけ優秀な歯学部生でも、ちょっと気を抜くと留年してしまうリスクが高まります。
私立歯学部を見てみると一度も留年することなく歯科医師国家試験も1回で合格した学生の割合が20%台の歯学部が2校、30%台の歯学部が5校もあります。これらの歯学部では、ほぼ7割、8割の学生が1回以上、留年していることになります。 特に私立歯学部では、順調に進級していくことが簡単では無いことが分かります。 文部科学省が発表しているデータには、「歯学部(歯学科)における留年・休学者の割合」というデータがあります。これは、歯学部在学中に一度でも留年・休学を経験した学生の割合を示すものです。 先ほど触れた九州大学歯学部は39.6%で、4割近い歯学部生が留年または休学を経験しています。 私立大学歯学部を見てみると、最も留年・休学経験者が少ないのは昭和大学(現・昭和医科大学)歯学部の20.6%で、大阪歯科大学の23.3%、東京歯科大学の27.8%と続きます。
一方で留年・休学者の割合が50%台の歯学部が5校、40%台の歯学部が6校あります。これらの歯学部では、半数程度の学生が一度または複数回、留年していると考えられます。 私立大学歯学部全体で見ると、6年まで一度も留年・休学していない学生の割合は41.2%となっています。私立歯学部の4割を超える歯学部生が一度ないし複数回、留年・休学を経験しるのが現状です。 厳しい数字ばかりのように見えますが、逆に言うと「私立歯学部生の半数以上は留年・休学を経験していない」ということになります。正しい勉強を重ねることが出来れば問題なく、歯学部を卒業出来るということです。「歯学部での正しい勉強」これが分かっているかどうかが非常に重要となります。
3. 留年を繰り返すとどうなるのか
歯学部で一度留年すると、その後のモチベーション低下や自信喪失につながるケースが多く見られます。
そして、残念ながら留年を一度経験した学生は、再び留年するリスクが高まるという傾向があります。
私立歯学部には「在学年限」や「留年回数の上限」が設けられており、それを超えると**最悪の場合「放校処分(退学)」**となってしまいます。
これは本人にとって大きな挫折であり、経済的・精神的な損失は計り知れません。
4. 歯学部生がつまずきやすいポイント
歯学部のカリキュラムは膨大かつ専門的で、以下のような科目でつまずく学生が多くいます:
・ 解剖学、生理学、生化学などの基礎医学
・ 歯内療法学、補綴学などの専門科目
・ 実習の技術習得
・ レポートやプレゼンテーションの提出
これらは座学だけでなく手技や判断力も求められるため、自己流での学習に限界を感じる学生が多いのです。
5. 予備校を活用するメリット
そこで活用したいのが歯学部生向けの予備校です。予備校のメリットは次のとおりです:
・ 自分の苦手分野に特化した指導が受けられる
・ 定期試験や進級試験に直結した内容の解説
・ 復習や予習のリズムを作れる
・ メンタル面での支えになる講師との出会い
特に歯学部生専門の予備校では、各大学の傾向を熟知した講師が対応するため、最短距離で得点力を上げる指導が可能です。 ただ、歯科医師国家試験対策をメインとする予備校がほとんどで、こういった予備校は歯学部の進級対策という面での経験値は低くなります。
6. オンライン個別指導という選択肢
近年、注目を集めているのが「オンライン個別指導」です。これは、インターネットを通じてマンツーマンの授業を受けられるサービスで、以下のような利点があります:
・ 全国どこに住んでいても受講可能
・ スケジュールを自分に合わせて柔軟に調整可能
・ 移動時間や交通費が不要 ・ 質問対応も問題ない
・ 必要な科目に絞っての受講
歯学部生は忙しい日々の中で勉強時間を捻出する必要があるため、空き時間を有効活用できるオンライン指導は非常に効率的です。
デントゼミのように、「歯学部進級に特化したオンライン個別指導予備校」であれば的確な指導が期待出来ます。
7. 予備校選びで重視すべきポイント
予備校を選ぶ際には、以下の点を確認しましょう:
1. 歯学部生専門の進級のためのカリキュラムがあるか
2. 自大学の試験傾向に対応しているか
3. 講師の専門性や実績
4. オンライン対応の有無
5. 質問対応が可能か、素早いか
6. 講師は生徒に寄り添うことの出来る講師か
特に「自分の大学に合わせた指導があるかどうか」は重要です。大学によって出題傾向や評価基準が異なるため、的外れな学習にならないよう注意しましょう。また、大学教員が講師を務める場合、自分の専門分野以外は詳しく無かったり、自分が歯学部で学んだ当時の古い感覚から抜け出せない講師もいます。最近は医科関連の学習内容も増えています。歯科医師免許と医師免許のダブルライセンス所持者の講師がいると心強いものがあります。歯科医師免許を取得して間もない講師であれば、年齢的にも近く、現在の歯科教育にも理解があるでしょう。
8. 効果的な活用法と学習スケジュールの立て方
予備校を最大限に活用するには、次のような方法がおすすめです:
・ 苦手科目の分析と優先順位づけ
・ 講師と相談して定期的な学習計画を立てる
・ 毎回の授業で疑問点をその場で解決
・ テスト直前期は総復習+演習中心に切り替える
・ 進級試験だけでなく国家試験を見据えた学習習慣の確立
自分ひとりではどうしても先延ばしにしてしまう学習も、定期的な授業や課題があるこ とで継続しやすくなります。
9. まとめ
歯学部、特に私立歯学部では進級の壁が高く、留年→再留年→放校という負のスパ イラルに陥るリスクがあります。だからこそ、早い段階で自分の弱点を知り、適切なサポートを受けることが重要です。
歯学部生を持つ親御さんも含めて、早めの対応を考えるといいと思います。 歯学部生のための予備校、特にオンライン個別指導型の歯学部進級予備校は、忙しい歯学部生にとって最適な学習環境を提供してくれます。通学不要で全国どこでも受講でき、マンツーマンで指導が受けられるこのシステムを、進級のための「切り札」として賢く活用しましょう。