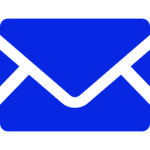歯科医師国家試験に不合格だった場合、次に向けての具体的な方法
1.歯科医師国家試験の合格出来ない人の4つの特徴
第118回 歯科医師国家試験を受けた歯学部生の方々、試験お疲れ様でした。3月14日に歯科医師国家試験合格発表がありますが、自己採点や採点サービスでおおよその結果が分かると思います。歯科医師国家試験は必修を8割超えていること、領域A・Bで下1/3に入っていなければ合格となります。
今回の記事は歯科医師国家試験を再度受験する方に向けて記載します。
歯科医師国家試験で不合格となってしまう人には特徴があります。自分の特徴を振り返り、そこを改善しつつ次の歯科医師国家試験に向けて準備を進めて下さい。
1-1自分の弱点と向き合わない人
1つ目の特徴として、「自分の弱点と向き合わない」ということが挙げられます。自分で「ここが苦手」、「こういうので落としそう」と心の中では分かっていても、そこを何とかようとしない人が少なくありません。苦手なこと、弱点分野は誰でも見て見ぬふりをしたいものです。しかし、それでは歯科医師国家試験の合格は危ういものになってしまいます。こういう人は先生が自分の苦手分野をきっちり強化してくれる個別指導がいいでしょう。
1-2実際の歯科医師国家試験の成績と模試の成績が乖離している人
2つ目は、「実際の国家試験の成績と模試の成績が乖離している」という特徴で、このタイプも多く見かけます。「模試の成績を見ると合格圏に入っているのに、実際の歯科医師国家試験では合格できない人」は、「知識の抜け」があります。特に、1年次、2年次で学ぶ基礎的な部分の知識が抜け落ちている傾向があります。実際の歯科医師国家試験で「必須」で合格基準を満たせないために、他は十分に合格ラインを超えているのに不合格となってしまいます。模試の成績にムラのある人も含めて「知識の抜け落ち」を直さない限り国家試験合格は厳しいものとなってしまいます。
1-3画像問題で、問題文をきちんと読まない人
画像問題とは言え、その問題で何が問われているのかを確認することなく解答してしまうのは、あまりにも無謀です。日頃の勉強の中で問題文をしっかり読むクセを付けるようにしてください。こういった人の中には、国語力が無いために「問題文を読んだつもりでいても、問題文で問われていることを理解できていない」ということに陥りがちな人も少なくありません。現在の歯科医師国家試験は「問題文の読解力」が欠かせません。デントゼミの歯科医師免許と医師免許の両方を取得している先生は「医師国家試験と違い、歯科医師国家試験では国語の読解力が必要」とおっしゃっています。この「問題文の読解力」は、問題演習の中で「正しく読めているか」を考えて行くしかありません。出来れば、個別指導で、「問題文の自分の理解が正しいか」を確認しながら問題演習を進めるといいでしょう。
1-4問題演習を甘く考えている人
歯科医師国家試験に合格できない人の4つ目の特徴は今、述べた問題演習に関するもので、「問題演習を甘く考えている人」です。真面目な人ほど、ノートをきれいにまとめることに力を入れる傾向がありますが、ノートをきれいにまとめることで満足してしまい、知識を使う練習を疎かにしてしまう人がいます。ノートをまとめることはいいのですが、知識は歯科医師国家試験で使えなければ意味がありません。知識を「歯科医師国家試験で使える知識」にするためには問題演習が欠かせません。
2.歯科医師国家試験で不合格になった場合は、どうしたらいい?
歯科医師国家試験に合格できない人の特徴を見て来ましたが、ここからは残念なことに不合格となった人の今後についての具体的な話です。
歯科医師国家試験不合格者は、予備校に入校するか母校に残り聴講生としての1年を過ごします。予備校を希望する場合は早めに入校を済ませることをおススメしますが、入校試験で高得点を取ることで学費が安くなることもありますので、そういった点も見ておくといいでしょう。母校に残る場合は、学務に問い合わせるだけで特に準備する必要はありません。
予備校に通うべきかどうかは自分の性格、出身大学、苦手教科、模試偏差値と卒業試験順位の相関度合いを見て判断することが多いと思います。自分で勉強できる方、規則正しい学習習慣のある方は予備校の夏講義、直前講義、習熟度チェックで事足りると思います。
一方で、生活が不規則になりがちな方、あまり自分を追い込んで勉強出来ない方は通年で予備校に通った方がいいでしょう。また模試の偏差値と卒業試験の順位が相関しない方は、どこかで知識がスキップしている可能性がありますので、講義を受け学び直しが必要になります。
母校で聴講生として通った方が良い方は、卒業試験だけに集中してしまい大学の授業が疎かになった方、病気で大学の講義を受けられなかった方などです。聴講システムが整っている大学は、聴講生でいいと思います。
歯科医師国家試験は終了したばかりですが、早くも来年の歯科医師国家試験まで1年を切っていますので、時間の使い方がとても大切です。膨大な量をこなす必要のある歯科医師国家試験ではありますが、限られた時間の使い方は結果に直結します。一度受けた講義を2回も3回も受ける必要はないと個人的には思っています。大切なのは「知識を使えるものにする」ことです。すなわちアウトプット中心の学習が大切です。インプット型の学びは効率が低く特別オススメする理由はありません。そして新卒の合格率が60%以下の大学は大学の講義の質が低い可能性もありますので、母校で聴講生をするより、予備校を利用した方がいいかもしれません。そこは自分で判断してください。
3.歯科医師国家試験に向けての予備校と母校の聴講生
ここからは、予備校の種類と母校で聴講生をするメリットとデメリットついて記載します。まずは予備校についてです。
予備校のなかにも集団講義で年間通して学習を進めていく集団講義型、すでに録画されている講義を視聴するオンライン配信型、ZOOM等を利用してオンラインで講師と対面して講義を受けるオンライン生講義(個別指導)型の大きく3つが挙げられます。
集団講義型のメリットとしては、出席することで持続的なモチベーションの維持となることや、1から系統だった講義を受けられること、講義のなかで問題演習を同時に行えること、他大学出身者と交流を深めることができることにあります。デメリットとしては、緩徐な進行になってしまうこと、自分のペースで学習を進めることができないこと、講義が一方通行になってしまい受け身となることで習熟が困難であること、があります。
オンライン配信型のメリットとしては、録画なので倍速にして高速学習が可能であること、苦手な範囲を局所的に学習することが可能であることがあります。デメリットとしては、集団講義と同じく一方通行となりますので、「なんとなく理解したような気」で終わってしまうこと、また、出席等のモチベーションのコントロールがないので途中でやめてしまうこともあり、個人のやる気に大きく依存してしまうこと、があります。
オンライン生講義(個別指導)型のメリットとしては、講師と1対1の対面であるため双方向のやりとりがあり理解を深めやすいこと、わからないことだけを選択して学習を進めることができること、受講場所がいつでもどこでも可能であること、自分の都合に合わせて受講できること、があります。またデメリットとしては、その場で生徒の質問にも答えていくため比較的進行が遅くなりがちということ、講師との相性によって大きく左右されること、オーダーメイドでの個別指導のため費用が比較的高くなりがちなこと、が挙げられます。
ここまで予備校について述べてきましたが、最後に出身大学の聴講生になることのメリットとデメリットについて記載していきます。メリットとしては、月5000円程度のところもあり比較的費用を抑えられること、6年生と一緒に講義を受けることで追い込み効果があること、各診療科における専門家の意見が聞けること、があります。デメリットとしては、時間・場所が大きく制限されること、自分のペースで学習できないこと、アウトプットの少ないインプット型であること、があります。
ここまでメリット、デメリットを記載してきましたが、1年はあっという間です。すぐにでも行動をおこし自分にあった学習方法で開始することが重要です。オンライン生講義(個別指導)型のデントゼミでは、比較的幅広い学習タイプに合わせることが可能です。
少しでも悩んでいる方はお気軽にご相談ください。