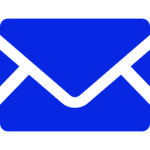第118回歯科医師国家試験、合格率60%台の厳しい状況が続くか?合格の秘訣はたった1つのことを守るだけ
1.歯科医師国家試験の合格率は60%台、40%が不合格
2025年2月1日(土)、2日(日)の2日間をかけて第118回歯科医師国家試験が全国8会場で行われました。
昨年の第117回歯科医師国家試験の合格率は国公立大学歯学部、私立大学歯学部など新卒・既卒の受験者全てを合わせた合格率は66.1%でした。
このうち国立大学歯学部全体の合格率は78.8%、公立大学歯学部の合格率は73.5%でした。また新卒だけの合格率は国立大学歯学部が90.2%、公立大学歯学部が79.1%でしたが、既卒生の歯科医師国家試験合格率は国立大学歯学部が46.2%、公立大学歯学部が58.1%と既卒生が苦戦していることが分かります。
私立大学歯学部に目を転じると、新卒・既卒を合わせた私立大学歯学部全体の合格率は62.0%で、私立大学歯学部の新卒の合格率は78.8%でした。一方で、私立大学歯学部既卒の歯科医師国家試験合格率は38.0%でした。国公立大学歯学部と同じように既卒生が苦戦していることが明確に分かります。
第117回歯科医師国家試験結果
| 総合合格率 | 新卒合格率 | 既卒合格率 | |
| 国立大学歯学部 | 78.8% | 90.2% | 46.2% |
| 公立大学歯学部 | 73.5% | 79.1% | 58.1% |
| 私立大学歯学部 | 62.0% | 78.8% | 38.0% |
| 認定等 | 15.4% | 10.0% | 33.3% |
| 全体 | 66.1% | 81.5% | 39.8% |
2.既卒の合格率は30%台、1回で合格しないと厳しい道が待っている
第117回の歯科医師国家試験の結果を見ると、国公立大学歯学部も私立大学歯学部も既卒の合格率が良くないことが目につきます。
歯学部生は国立であっても公立であっても私立であっても、卒業と同時に歯科医師国家試験に合格しないと、そこから厳しい道が待っていることが分かります。
歯科医師国家試験は付け焼刃の知識では合格は到底望めません。歯学部在学中、各学年でのしっかりした学習の積み重ねが非常に重要であることが分かります。
3.見かけの合格率に惑わされてはいけない。その理由とは?
もう1点、歯科医師国家試験合格率を見る時に、絶対に気を付けてもらいたいことがあります。それは、「出願者数と受験者数の差」です。
ざっくり言うと「出願者数は6年生の人数」で、受験者数は「6年生のうち、歯科医師国家試験を受けさせて貰えた人数」言葉を代えて言うと「6年生のうち、卒業認定を貰えた学生数」です。
第117回歯科医師国家試験の結果を見ると私立歯学部新卒の合格率は78.8%となっています。公立大学歯学部とほぼ同じ新卒合格率です。一見、それほど問題の無い結果のように見えます。私立大学歯学部の学生や保護者の皆さんは、これで安心してはいけません。公立大学歯学部とそん色のない合格率には理由があります。その「理由」を見て行きましょう。
第117回歯科医師国家試験の、私立大学歯学部全体の出願者数は1729人ですが、受験者数は1336人です。「私立大学歯学部6年生のうち393人、22.7%の6年生が卒業認定を受けることが出来ずに歯科医師国家試験を受けることが出来なかった」、ということです。
国公立歯学部生の皆さんも、もちろんですが特に私立歯学部生の皆さんは1年生のうちから着実な知識の積み重ねが非常に重要です。歯学部6年生での卒業試験は6年間で学んだ膨大な量を試されます。「6年になってから頑張る」では到底追いつきません。
第117回歯科医師国家試験 新卒の出願者数と受験者数
| 新卒出願者数 | 新卒受験者数 | 差 | |
| 国立大学歯学部 | 533人 | 530人 | 3人 |
| 公立大学歯学部 | 86人 | 86人 | 0人 |
| 私立大学歯学部 | 1729人 | 1336人 | 393人 |
4.歯科医師国家試験、落ちるはずのない人が落ちる理由
実際の歯科医師国家試験では、「しっかり勉強をして模試の順位も悪くないのに、なぜか不合格になる人」がいます。
こういった「落ちるはずがないのに落ちる」人達の特徴として「必修問題で落とす」傾向を挙げることが出来ます。こういった人たちは、3年次や4年次以降の臨床の内容については、しっかりとした知識があるものの1年次、2年次の基礎医学が疎かになっていることが多く見られます。後で述べますが必修問題には「基準点」が設けられていますので、他の部分では合格基準を十分に満たしているにも関わらず、必修問題が基準点に届かず不合格となってしまうのです。
このことからも、歯学部入学後は1年次から歯科医師国家試験を見据えて着実に知識を積みあげて行くことが欠かせないことが分かります。「6年生になってから歯科医師国家試験に向けて頑張ればいい」と考えていると、やるべきことの多さから「間に合わない」ことになってしまいます。
歯学部の学生の皆さんは、「将来、歯科医師になる」ということで歯学部に入学したと思います。その思いを活かすためには歯学部で確実に進級し、6年生での卒業試験と歯科医師国家試験の両方を突破する必要があります。1年生から着実に知識を積み重ね、実習もその意味を深く理解することが欠かせません。「ギリギリだったけど進級出来たら、オッケー」は、「知識の積み残しがある」ということになりますので、非常に危険な考えです。
最近の歯科医師国家試験では、「全身疾患に関する内科学」、「多職種連携」など、医科の領域まで求められます。当然、歯学部の学習内容にも医科関連のものが増えて来ています。歯学部生は医科関連の内容が弱い傾向があります。ここが曖昧なままだと、卒業試験もそうですし歯科医師国家試験の合格も危うくなります。医科関連の分野は出来れば、歯科医師免許に加え、医師免許も持った医科にも詳しい先生に教えて
もらうといいでしょう。「医科の一部分ではなく、医科全体を知っているからこそ指導できる」という面は間違いなくあります。メルオンでは歯科医師免許と医師免許のダブルライセンスを持っている先生や歯科医師免許取得後、医学部へ編入学して医学部の卒業間近の先生等、医科全体にも詳しい先生が揃っています。
5.歯科医師国家試験の問題数と出題基準
歯科医師国家試験の話に戻りましょう。歯科医師国家試験では必修問題が80問、一般問題(領域A・領域B)と臨床実地問題が280問の合計360問が出題されます。
配点は必修問題と一般問題が1問1点、臨床実地問題は1問3点となります。臨床実地問題は1問3点と配点が高く、合計点の半数近くが臨床実地問題となります。歯科医師国家試験合格のためには臨床実地問題は問題数が少ないからと言って、手を抜くことは出来ません。
歯科医師国家試験の出題基準は下記のようになっています。
【必修の基本的事項】
・医の倫理と歯科医師のプロフェッショナリズム
・社会と歯科医療
・予防と健康管理・増進
・人体の正常構造・機能
・人体の発生・成長・発達・加齢変化
・主要な疾患と障害の病因・病態
・主要症候
・診察の基本
・検査・臨床判断の基本
・初期救急
・治療の基礎・基本手技
・一般教養的事項
【歯科医学総論】
・保健・医療と健康増進
・正常構造と機能、発生、成長、発達、加齢変化
・病因、病態
・主要症候
・診察
・検査
・治療
・歯科材料と歯科医療機器
【歯科医学各論】
・成長・発育に関連した疾患・病態
・歯・歯髄・歯周組織の疾患
・顎・口腔領域の疾患
・歯質・歯・顎顔面欠損と機能障害
・配慮が必要な高齢者・有病者・障害者等に関連した疾患・病態・予防ならびに歯科診療
※歯科医学各論において、出題割合の約6%を歯科疾患の予防・管理に関する項目から出題する
歯科医師国家試験には必修問題、領域A・Bそれぞれに合格基準が設けられていて、合格のためにはこの合格基準を全てクリアしないといけません。必須問題の合格基準は「80点満点で64点以上」など絶対評価ですが、領域Aと領域Bはそれぞれ相対評価になりますので、合格基準は毎回変わります。絶対評価は合格基準のイメージがつかみやすいのですが、相対評価は「歯科医師国家試験受験者の中で自分はどうなのか」となりますので、なかなか基準がイメージしにくいかもしれません。歯科医師国家試験の模試などで自分の位置を把握するといいでしょう。
6.まとめ
これまで述べてきたように歯科医師になるためには歯学部の卒業試験そして歯科医師国家試験という2つの大きな壁を乗り越える必要があります。この2つの壁を乗り越えるためには、歯学部1年次からの着実な積み重ねこそが何より大切です。
現在の歯学部、特に私立大学の歯学部では留年する学生も多くなっています。留年してしまう学生は何度も留年を繰り返してしまう傾向があります。
こういった歯学部生の大きな特徴は「勉強の仕方が分かっていない」ことです。歯学部生には歯学部生としての正しい勉強の進め方があります。ここが分かっていないため、留年したり卒業試験を乗り越えられなかったりします。これでは、歯科医師国家試験を受けることも出来ません。
万一、歯学部での進級に不安を感じたら様々なタイプの歯学部生を指導した経験豊富な先生やデントゼミのような歯学部進級に特化した予備校に相談するといいと思います。
歯科医師国家試験合格の秘訣は「1年次からの確実な積み重ね」に尽きます。誰かの手を借りた方がいいのであれば、1年次からでも手を借りて留年などすることなく、一気に歯科医師国家試験合格まで突き進んで下さい。多くの歯学部生を後押ししてきたオンライン個別指導の歯学部進級予備校デントゼミも、いくらでもお手伝いを致します。